剣道とともに20年近く

今日は水曜日。
剣道の稽古の日です。
これまでは月・木で稽古に参加していた次女。
しかし道場の方針で、小学生・中学生は水・金・日の稽古を基本に。という事になりました。
以前は中学生は一般と稽古だったので、一般の稽古の月・木に参加していました。
ただ一般の稽古に参加してはダメということではない。
あくまでも基本は小中学で、水・金・日の稽古。
でも次女は金曜日は英語があるので、金曜は稽古には参加できません。
そこで水曜日と日曜日に参加して、月曜日の一般の稽古にも参加する事にしました。
中学生になってから、ずっと一般での稽古に参加していたので、小中学生の稽古では物足りない感じもします。
同じ中学生がいれば良いけど、なかなか参加率は低いし、いても年下の子なので、一般との稽古のような厳しさがありません。
次女が小学校を卒業するまでは、ずっと水曜日は剣道の稽古でした。
それこそ、息子が剣道をやっていた時からですので、もう20年近くになりますね。
息子、長女、次女と、ずっと剣道続きです。
よく私のブログを見て、私が剣道をしていたと思われる方がおられます。
親がやっていたから子供達もやっている。そう思われるのだと思います。
まぁ、私も試合の結果など、まるで自分がやっているかのように、感想書いたりしていますからね(笑)
私は剣道は全くの未経験です。
息子が剣道を始めて、初めて剣道を知ることになりました。
私自身は、中学〜高校と軟式テニスをやっていました。
剣道は、高校の時に、同級生が部活でやっていたのを見たくらい。
全く剣道の知識もないまま、息子が始めたことで、剣道の世界を知ることになりました。
最初は全くルールも分からないし、試合を見ても、何が決まったのかさっぱりでした。
剣道の決まり手は、面と胴と小手。高校生以上は突きもありますが。
試合で面を打っていても、審判の旗が上がる時と上がらない時の差が、全くわかりませんでした。
ちゃんと竹刀の先端から20cmくらいまでの間で、面に当たっていないといけない。
さらに当たっていれば良いのではなく、面を打つまでの所作、そして打った時の声、さらには打ち終わった後の残心(所作)まで、全て見て審判は旗を上げます。
これが、最初はさっぱりわからなかった。
でも、子供の稽古や試合を見るにつれ、だんだんとわかるようになってきた。
これって保護者によくあるパターンらしく、先生方は「見取り稽古」と呼んでいました。
少しずつ剣道を理解して、動きも見れるようになっていくんですね。
剣道はスポーツでは無く、武道なので、勝敗だけが全てではありません。
勝っても負けても、ちゃんと礼節をわきまえて、相手と試合をする必要があります。
だから剣道は、必ず礼に始まり、礼に終わる。
例え1本が決まっても、それを喜んではいけません。
心の中で「よしっ!」と思うのはOKだけど、それを表に出してはいけません。
もしガッツポーズなどしようものなら、1本を取り消されてしまいます。
それでも試合なので、みんな勝ちたい気持ちは当然あります。
むしろそれがなければダメです。
剣道は、剣を交わして勝負しますが、己との戦いでもあると思います。
だから負けたのは、己の稽古不足。
勝負事なので、勝敗は必ずある。
勝った試合よりも、負けた試合の時の方が、学ぶことが多いのだと思います。
また、まるで自分がやっているかのように、書いていますが、私は未経験者です(笑)
でも、子供たちの剣道を通して、剣道の素晴らしさを教えてもらっています。
もっともっと、たくさんの子供達に、剣道を経験してほしいと思っています。
次女も今年は受験生なので、稽古に参加するのも、この夏までかな?と思っています。
なので、私の長年続いてきた、剣道の付き添いも、この夏までかも知れません。
高校になっても次女が剣道を続けるのかは、本人に任せたいと思います。
仮に高校でも続けるとしたら、高校の部活でやることになる。
そうなると、おそらく道場の方には来ることはほぼほぼない。
20年近く続いて来た、剣道の稽古の付き添いも、もう終わりが見えて来た感じです。
保護者の中でも、こんなに長い期間、剣道に携わっている人間はいません(笑)
私もそろそろ卒業の時ですね。
でも、剣道の試合見るのは好きなので、やっぱり次女には続けてほしいなぁ。


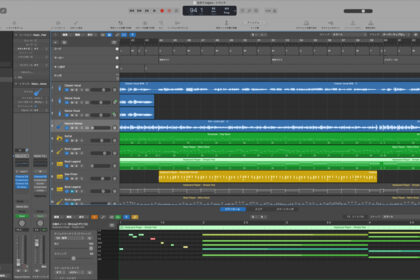


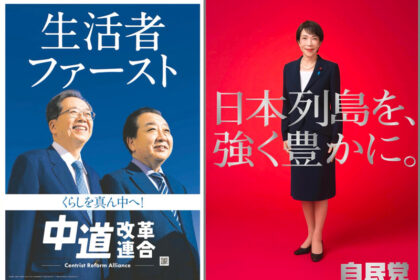

コメントを残す