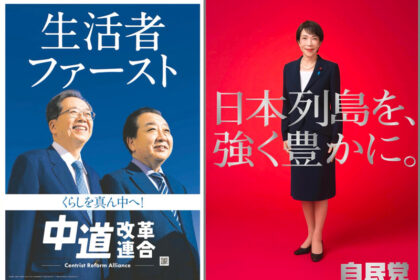人の輪を広げていこう
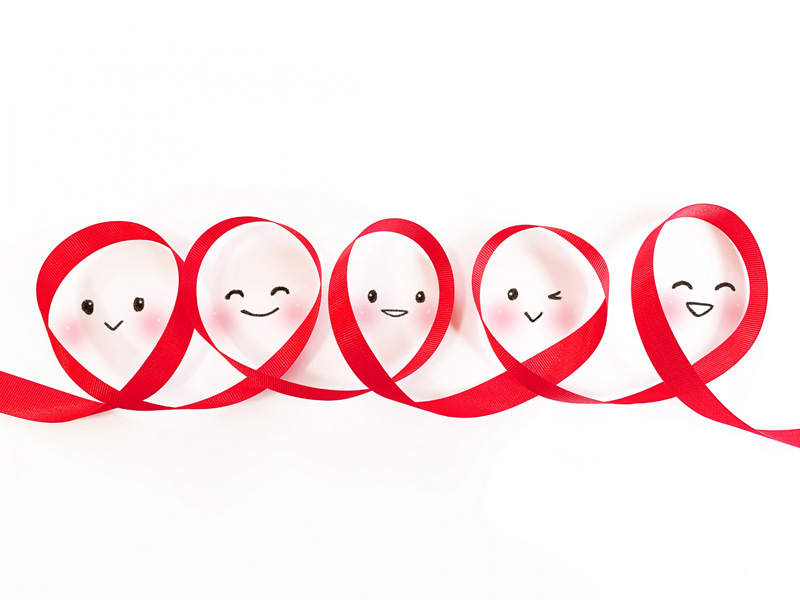
今日は学校運営協議会合同会議があり、参加して来ました。
会議といっても、今回は新年度に入って間もないので、市から説明に近い内容。
新しく学校運営協議会の委員になった人もいるだろうから、いろいろと説明に近い会議でした。
しかし、これまでとは明らかに違うことも。
それは市からのお願いとして、これまでの学校運営協議会から、アップグレードしてほしいととの事。
「アップグレード」とは言っていないけど、内容はそれに近い話。
これまでは、学校運営協議会を学期ごとに開いていました。
1学期に、校長先生から学校の方針を説明していただき、2学期に学校の様子などを説明していただき、3学期に総括をする。
これで1年間が終わっていました。
どうしても学校の方針の承認をするだけで、そこから先に進んでいない。
これは私もここ数年感じていたことで、「意味あるのか?」と思っていました。
同様に市も問題としていたと言う事ですね。
地域コーディネーターにも同じことが言えて、学校からボランティアの要請を受けて動くのではなく、こちらから積極的に動いていかないと、何も変わらないと思う。
学校運営協議会にしろ、地域コーディネータにしろ、受け身ではだめで、自主的に動いていくことが求められている。
しかしいきなり「自主的に」と言われても、何からやれば良いのか、きっと誰もわからない。
他の地域の取り組みを聞いても、地域によって状況は異なる。
自分の地域で何ができるのか?を考えていく必要がある。
私はこの2〜3年、ずっと「まずは地域づくり」と考えてきました。
私の校区の小学校は、8割くらいが新しい町の子供達です。
しかし新しい町の住民は、コミュニティーが出来上がっていません。
私の住んでいる町も、知らない人がたくさんいる。
私は以前、自治会の役員をしていたので、多少は顔馴染みの方がいるけど、それでも大半の人は知らない。
きっと隠れた人材が、たくさん眠っていると思う。
その人材を掘り起こすところから、はじめて行きたいと思っています。
1年2年で変わるものではないと思うので、少しずつ人の輪を広げて、人材発掘をして行きたいと思います。
人が集まるようになれば、自然とボランティアの輪も広がる。
そうなれば、学校運営協議会も、地域の学校として何をすべきかが、見えてくると思う。
結局は地域の活性化が必要なんですよね。
同じ地域に住んでいながら、隣の家のひとくらいしか知らないような地域では、活性化は起きない。
地域の人が、学校に集まってきたくなるような、仕組みを考えて行きたいですね。
どこまでできるのかわからないけど、自分ができることを、できる範囲で、楽しんで行きたいと思います。